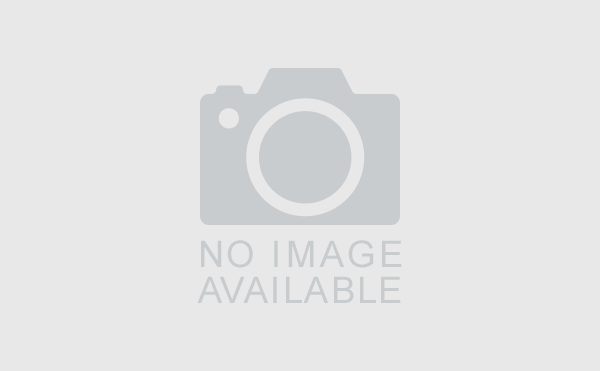系統用蓄電池用地の農地転用
こんにちは。農地専門の行政書士の松田です。
今日は、系統用蓄電所を設置する場合の農地転用について記載します。
農地転用と系統用蓄電池設置に関する基本的な知識
~宮城県内での許可申請のポイント~
再生可能エネルギーの普及に伴い、電力の安定供給を支える「系統用蓄電池(送電網に接続する大型蓄電池)」の設置が全国的に進んでいます。その設置候補地として、農地が選ばれるケースも出てきています。しかし、農地に設備を設置するには「農地転用」の手続きが不可欠です。
本記事では、農地転用制度の概要と、宮城県内で系統用蓄電池を設置する際の留意点について、行政書士の視点から解説します。
系統用蓄電池とは?
系統用蓄電池とは、再生可能エネルギーなどで発電された電気を一時的に蓄えておき、必要なときに送電系統へ放電することで電力需給のバランスを調整する設備です。大規模な蓄電池を設置するには、広い土地とインフラ接続の両面が求められます。
農地に設置する際に必要な「農地転用」
日本では農地の保全が重視されており、農地法に基づいて農地の転用には原則として許可が必要です。
蓄電池の設置も例外ではなく、農地を電気設備の敷地として利用するには、以下のいずれかの手続きが必要になります。
農地転用の区分
- 農地法第4条許可:所有者自身が蓄電池を設置する場合
- 農地法第5条許可:第三者が転用を目的として農地を取得・使用する場合
宮城県内での農地転用の現状と注意点
宮城県内では、現時点で系統用蓄電池の設置に関連する農地転用許可の事例は多くありません。そのため、一律に「この面積なら大丈夫」というような基準(いわゆる適正面積)が明確に示されていないのが実情です。
✅ 適正面積の判断について
蓄電池の設置台数、設備レイアウト、電力会社との接続条件、排水や防火対策の有無など、さまざまな事情を考慮した上で、各案件ごとに行政と個別に相談しながら進める必要があります。
また、農地の区分、地域計画除外の必要なども関係するため、事前協議が極めて重要です。
行政書士に依頼するメリット
農地転用手続きは、単に申請書を提出すれば終わるものではありません。
現地の状況、地目、法的制限、自治体の運用基準を総合的に検討し、「そもそも可能かどうか」を見極める初期判断が非常に重要です。
行政書士は以下のような支援を行います:
- 必要手続きの整理と事前相談の同行・代行
- 添付図面や事業計画書等の書類作成
- 農業委員会との連絡調整や補足説明の対応
- 関係法令(都市計画法・建築基準法など)との整合性確認
まとめ
系統用蓄電池の設置はエネルギーの安定供給や地域活性化に貢献する一方で、農地という公共性の高い資源を転用する以上、手続きは丁寧かつ慎重に行う必要があります。
特に宮城県内では前例が少ないため、行政との事前協議や情報収集が成功の鍵となります。
計画段階からのご相談を通じて、スムーズな申請と許可取得をサポートさせていただきます。
当事務所では、農地転用に加え、消防法、再エネ条例、開発協議申請等にも